こんにちは。グロースコンパスのイシマキです。
「最近、原価が高すぎて利益が出ない」
「卵も米も野菜も高くて、仕入れの見直しを検討している」
「価格転嫁したいけど、お客さん離れが怖くて踏み切れない」
そんなお声を聞く機会がここ数年で格段に増えました。実際、2025年3月の帝国データバンクの調査によれば、飲食店の94.6%が仕入れ価格の上昇に直面しており、これは全業種の中で最も高い水準です【出典:帝国データバンク 景気動向調査2025年3月】。
なぜここまで仕入れ価格が上がっているのか、そしてそれに対してどのように備え、乗り越えるべきか。今回は、飲食業界を取り巻く仕入れコスト上昇の背景から実際の経営対策まで、解説します。
なぜ仕入れ価格が上がっているのか? ― 3つの主因

- 原材料価格の高騰
コロナ禍からの需要回復や地政学的リスク(ウクライナ情勢等)に加え、国内農業の担い手不足や気候変動の影響で、米・卵・葉物野菜・食用油などが軒並み高騰しています。
農林水産省のデータによれば、2024年〜2025年にかけて食用卵の卸売価格は1.5〜2倍に上昇しており、外食産業にとっては特に打撃の大きい指標です。 - 円安と輸入食材の値上がり
2025年春時点で為替は1ドル=150円台。外貨建てで仕入れるワイン、チーズ、パスタ、オリーブオイル、冷凍肉などの価格が大幅上昇しています。特に洋食・バル業態では、メニュー構成上のダメージが顕著です。 - 物流・エネルギーコストの増加
2024年に施行された「働き方改革関連法」の影響でドライバーの時間外労働が制限され、物流業界の人手不足が加速。これにより配送費や冷蔵輸送費などが上がり、仕入価格全体に跳ね返っています。
飲食店が特に深刻な理由とは?
帝国データバンクの調査では、2022年以降、12ヶ月連続で9割を超える飲食店が「仕入れ価格が上昇した」と回答しており、その深刻度は突出しています。しかも「非常に上昇した」という回答も1〜2割を占め、実質的な“コストショック”を経験している事業者が少なくありません。
たとえば、以下のような業態・商品で特に負担感が大きい傾向があります。
- 和食・定食系:
米・味噌・漬物・魚など複数食材で影響が大きい - 居酒屋:
鶏卵、鶏肉、油など、原価率の高い人気商品が多い - 洋食・バル:
チーズ・輸入肉・オリーブオイル等、為替直撃の食材が多い
価格転嫁の壁とその差
もうひとつ問題なのは、「価格転嫁」が思うように進んでいないという現実です。
同じく帝国データバンクの調査では、飲食店の販売価格を上げた割合は64.9%にとどまり、仕入れ価格上昇との差(94.6%)は約30ポイント。この差額は、飲食店が“自己負担”で吸収していることを意味します。
「値上げしたらお客さんが来なくなるのではないか」という心理的ハードルに加え、地域相場や競合他社とのバランスを考慮して価格転嫁に踏み切れない飲食店が多いのが現実です。
今、飲食店が取るべき5つの現実的な打ち手

価格転嫁が難しい中、どのように経営を守っていくべきか。ここでは、中小企業診断士の立場から、実際に効果があった具体策を紹介します。
仕入れ先・取引条件の見直し
仕入れ価格の高騰が続くなか、仕入れ先や取引条件を見直すことは、経営改善の第一歩です。価格交渉だけでなく、食材の選定基準や調達ルートを見直すことで、コストを抑えつつ品質を維持することが可能になります。
地場農家との直接契約、地産地消へのシフト
卸業者経由ではなく、地域の農家や漁師と直接契約することで、中間マージンをカットし、鮮度の高い食材を安価に安定供給できる可能性があります。また、「地産地消」は地域の食材を使ったメニューとしてPR要素にもなり、集客やブランディングにも寄与します。例えば「○○産の無農薬野菜使用」などの表記は、健康志向の高い顧客に対して強い訴求力を持ちます。
単価より「ロス率」「歩留まり」の高い食材へ
一見すると安価な食材でも、可食部が少なく廃棄が多ければ結果的にコスト高になります。逆に、やや高価でもロスが少なく歩留まりの良い食材を選ぶことで、1食あたりの原価を抑えることが可能です。例えば、骨や筋が少ない部位の肉や、カット済みで使いやすい野菜などは、仕込みの効率化にもつながり、トータルコストを下げる効果があります。
生鮮→冷凍素材への切り替えも一つの選択肢
価格変動が大きく、日持ちしない生鮮品を多く使用している場合は、品質の高い冷凍素材への切り替えも検討すべきです。特に冷凍技術の進化により、味や食感を損なわず保存可能な商品が増えています。これにより廃棄リスクが減り、食材ロスの削減と業務の平準化にもつながります。飲食店の現場では、冷凍食材をうまく使いこなすことが“省人化”や“時間のゆとり”を生む重要な手段となっています。
メニュー構成の再設計
食材価格が高騰する中、同じ価格帯で提供を続けることは店舗の利益を圧迫しかねません。今こそ、メニュー全体の構成を見直し、利益率の向上と顧客満足の両立を図ることが求められます。以下はそのための具体的な手法です。
原価率の高い商品を値上げ、あるいは限定提供に
看板メニューや人気商品でも、現在の価格設定のままでは赤字になるケースがあります。そうした商品については、思い切って値上げを行うか、「限定メニュー」として提供頻度や数量をコントロールする戦略が有効です。限定性を打ち出すことで、プレミアム感を演出し、値上げに対する顧客の納得感を得やすくなります。また、ポーション(量)の調整によって原価を抑える工夫も有効です。
セット化で満足感を保ちつつ利益率を確保
単品では原価が高く利益が出にくい料理でも、副菜やドリンクなどを組み合わせたセットメニューにすることで、全体の利益率を底上げすることが可能です。たとえば、原価率の低いサラダやスープ、漬物などを組み込むことで、「お得感」や「満足感」を演出しながら、店舗としての粗利を確保できます。また、セット化は客単価アップにもつながるため、売上向上の一手にもなります。
新メニューで高単価・高粗利商品を開発
仕入れ状況や季節に応じて、高粗利かつ単価の高いオリジナルメニューを開発することで、利益率を改善できます。たとえば、「地元産ブランド肉を使った炙り丼」や「季節限定の創作メニュー」など、限定性・ストーリー性を持たせることで、価格に対する価値を感じてもらいやすくなります。こうしたメニューはSNSなどでの拡散も狙いやすく、新たな顧客層の獲得にも寄与します。
SNSや店頭での価格改定理由の丁寧な発信
価格改定を実施する際、多くの飲食店が恐れるのは「お客様離れ」です。しかし、理由や背景を丁寧に伝えることで、顧客の理解と共感を得ることが可能です。むしろ、このような発信は、誠実な姿勢として顧客からの信頼を得るきっかけにもなります。
「なぜ値上げしたのか」を明示することで理解を得る
価格改定の背景にある仕入れ価格の上昇、人件費やエネルギーコストの増加などを、わかりやすい言葉で丁寧に説明しましょう。ポイントは“企業の都合”ではなく、“店舗を継続して運営していくための必要な選択”であることを誠実に伝えることです。たとえば、以下のような文言が効果的です。
「当店では、品質を維持しつつ今後も営業を続けていくために、やむを得ず一部商品の価格を改定させていただきました。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。」
このような表現は、店頭のポスターやメニュー表への記載、SNS投稿など、複数のチャネルで繰り返し発信することが重要です。
地域・食材のこだわりや背景も伝えると効果的
価格改定だけでなく、「なぜその商品に価値があるのか」もセットで伝えることが、価格以上の“納得感”を与えるポイントです。たとえば「〇〇県産の特別栽培米を使っている」「契約農家から直送される旬野菜を使用」など、素材へのこだわりを具体的に伝えると、顧客はその背景に共感しやすくなります。単なる“値上げのお知らせ”ではなく、“価値を伝えるストーリー”として情報発信を行うことが、価格改定への理解を促進します。
また、動画や写真を活用したビジュアルコンテンツをSNSで発信することで、より伝わりやすく、拡散性の高いアプローチが可能になります。
省人化・業務効率化の投資(補助金活用)
人手不足や人件費の高騰は、今や飲食業界全体の課題です。そのなかで、省人化と業務効率化を図るための設備投資は、売上減少を補い、店舗の持続可能性を高めるために非常に重要です。導入にあたっては国の補助金制度も活用できるため、初期費用の負担軽減も期待できます。
オーダーシステム、セルフレジ、予約管理ツール
モバイルオーダーやQRコード決済に対応した注文システムを導入することで、ホールスタッフの業務負担を軽減し、ピークタイムの混雑緩和にもつながります。また、セルフレジの導入によりレジ対応を最小限に抑えることが可能となり、人件費削減と会計ミス防止にも効果があります。さらに、予約管理ツールを活用することで、電話対応の時間を削減できるほか、来店予測や顧客管理にも役立ち、再来店率の向上にも貢献します。
配膳ロボットや食洗機の導入
人手が足りない店舗では、配膳ロボットや食洗機といった機器の導入が、労働負担の大幅な軽減と効率化を実現します。配膳ロボットは料理の運搬を自動化することでホールスタッフの移動距離を減らし、限られた人数でもスムーズなサービスが可能になります。一方、食洗機は洗浄業務を大幅に短縮できるうえ、衛生面の向上にも寄与します。いずれも導入効果が明確なため、少人数オペレーションの店舗には特に有効です。
これらは国の補助金対象にもなりやすいです
オーダーシステムや配膳ロボット、食洗機といった業務効率化ツールは、「IT導入補助金」や「業務改善助成金」などの補助対象となることが多く、費用の3分の2〜4分の3程度が補助されるケースもあります。補助金を活用することで、初期投資のハードルを下げつつ、生産性の高い経営体制を構築することが可能になります。申請には、事業計画や見積書の提出が必要となるため、専門家に相談しながら進めるとスムーズです。
あえて価格を据え置き、FL比率で利益を管理するという選択
必ずしも価格改定が唯一の打ち手ではありません。価格を変えずに利益を確保したい場合、「FL比率(Food:食材費+Labor:人件費)」を経営の基準として設定し、これを一定以下に抑えることで、利益を守るという戦略も有効です。一般的に、FL比率は60%以下が望ましいとされており、人件費の調整、業務効率化を組み合わせることで、価格を維持したまま収益体質を改善できます。
この考え方は、値上げによる顧客離れを避けたい場合や、競争が激しいエリアで価格競争力を維持したい場合に特に有効です。例えば、業務効率化のための設備投資、作業工程の見直し、アルバイトのシフト効率化、調理オペレーションの標準化などを通じて、FL比率を日々モニタリングしながら最適化することが、価格を動かさずに利益を残す鍵となります。特に飲食店にとってIT化や業務効率化のための投資は非常に有効で、これら投資に関して活用できる補助金は上記の通り多数あります。前向きに検討してみてください。
売上以外の収益源の開拓
飲食業界では「店内飲食」だけに収益を依存するリスクが顕在化しています。営業時間や客席数の制限、天候・社会情勢に左右されやすい店舗営業に加えて、人手不足も重なり、売上の安定化が難しくなってきました。こうしたなかで、新たな収益源を開拓し、事業を多角化する動きが重要になっています。
テイクアウト・デリバリー強化
イートインに比べて回転数の概念に縛られず、追加の売上を確保できるテイクアウト・デリバリーは、今や多くの飲食店にとって不可欠なチャネルです。特にランチタイムの弁当販売や、夜の家庭向けお惣菜などは、少人数オペレーションでも回せるため、営業効率が高まります。Uber Eats、出前館、menuなどの外部プラットフォームの活用に加え、自社による電話注文やLINE公式アカウントなどでの受付体制を整えることで、利益率の改善とリピーター獲得が狙えます。
また、テイクアウト・デリバリー向けの商品は原価計算や包装資材コストの見直しが重要です。容器の工夫やメニューの絞り込みにより、利益率を確保しやすくなります。
店舗オリジナル商品(ソース・漬物等)のEC展開
近年、飲食店の味やブランドを「家庭でも楽しみたい」というニーズが高まっています。店舗で人気のソース、ドレッシング、タレ、漬物、スパイスなどを商品化し、オンラインで販売することで、新たな収益源を確立することができます。ECサイト(BASE、STORES、Shopifyなど)の構築や、InstagramなどSNSを活用した販促を組み合わせることで、全国にファン層を広げることが可能です。
特に「〇〇店の人気メニューの味が家でも楽しめる」といったストーリー性を持たせることで、購入意欲を刺激しやすくなります。店頭販売とECを連動させることで、クロスセルやブランディング効果も期待できます。商品開発やECサイト構築にももちろん補助金が活用できます!
補助金・助成金の活用で「攻めの守り」を

政府もこの状況を重く見ており、飲食業を含む中小企業への支援策が充実しています。
活用可能な代表的な制度は以下の通り
- 小規模事業者持続化補助金:
設備導入、集客強化など最大250万円 - IT導入補助金:
予約管理・顧客管理・POS導入などに最大350万円 - 業務改善助成金:
人件費と生産性向上をセットで支援 最大600万円
申請には事業計画の作成や実行スケジュール、見積の整理などが必要ですが、中小企業診断士や専門家の支援を受けることで採択率も高まり、実効性のある計画が実現します。
最後に:価格が上がる今こそ、経営の「棚卸し」を
仕入れ価格の上昇は、一過性ではなく今後も続くと見られています。逆に言えば、今こそ業態を見直し、メニューを再構成し、経営体質を強くするチャンスでもあります。
- 原価と利益のバランスは適正か?
- メニューや仕入れ先に「惰性」はないか?
- コスト削減だけでなく「価値提供」も同時にできているか?
こうした視点で、自店の経営にしっかりと向き合うことが、これからの飲食業には求められます。
補助金・助成金の活用についても「自分の店が対象かどうか分からない」「どれが合っているか知りたい」といったご相談も含めて、専門家が伴走いたします。まずは気軽にご相談ください。





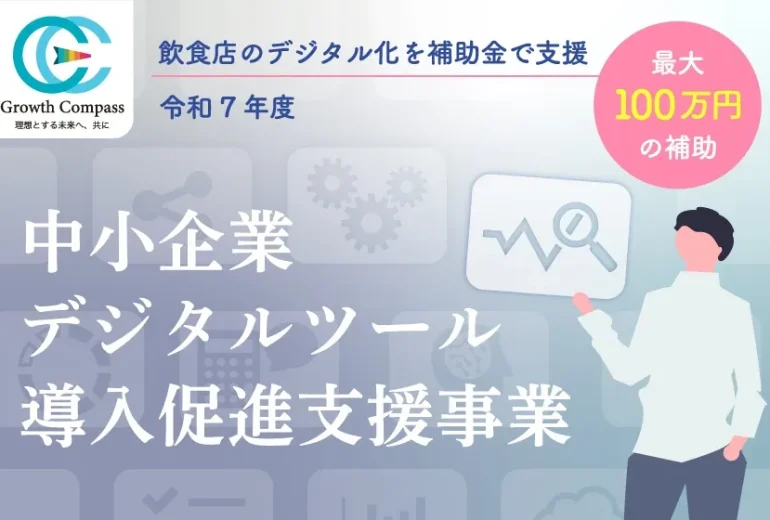

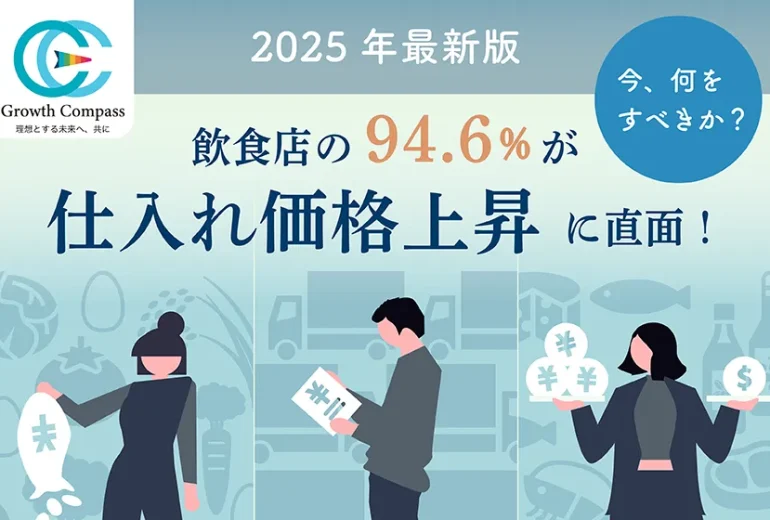
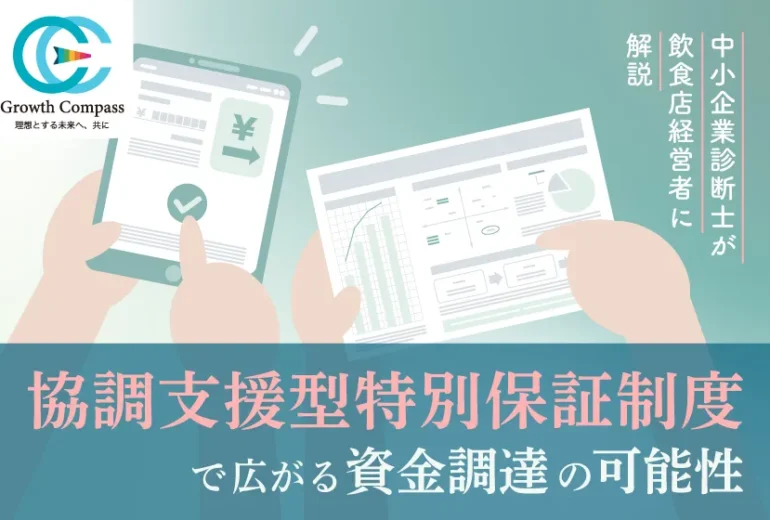
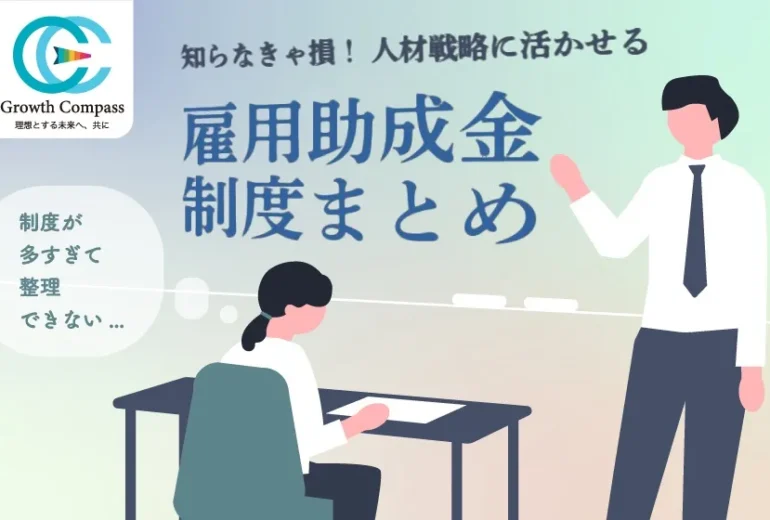

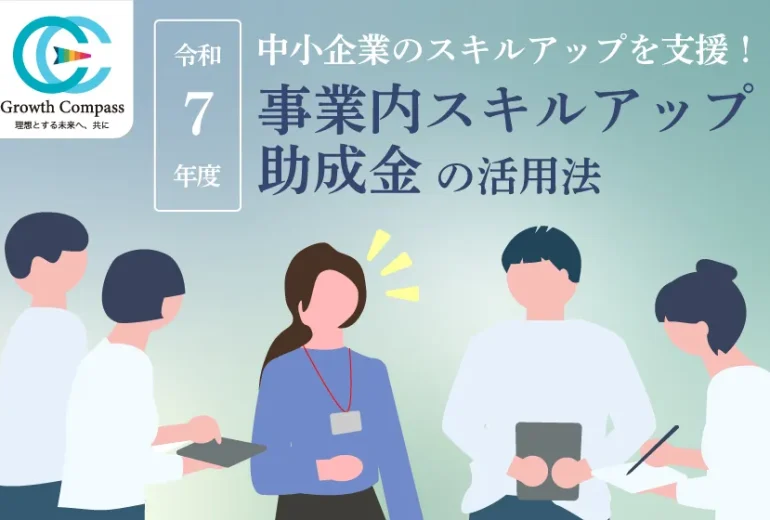
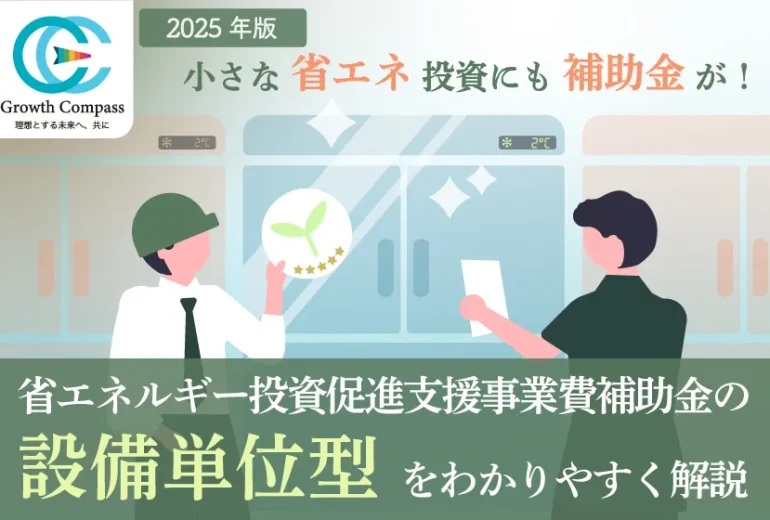
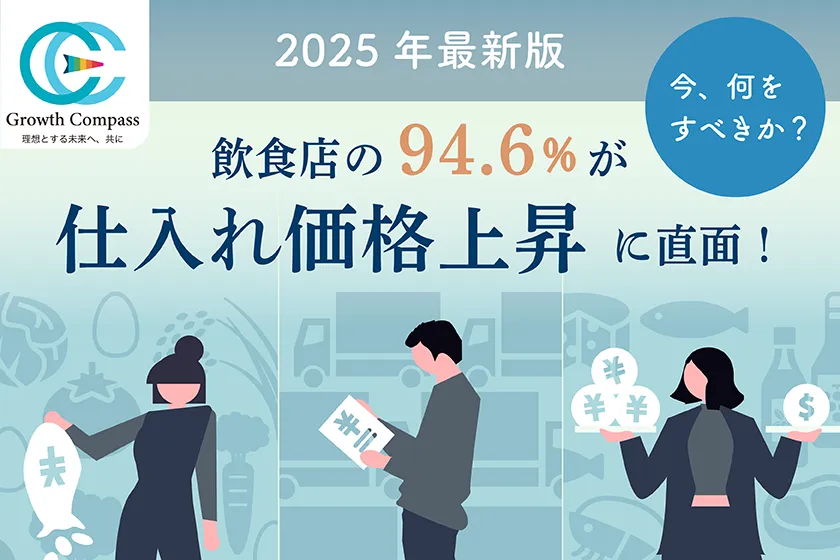



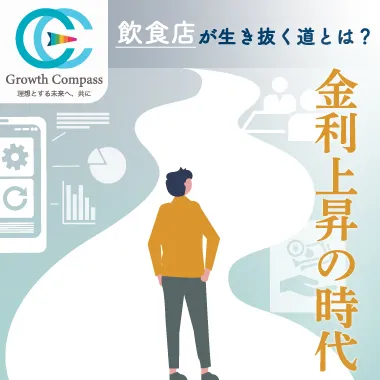


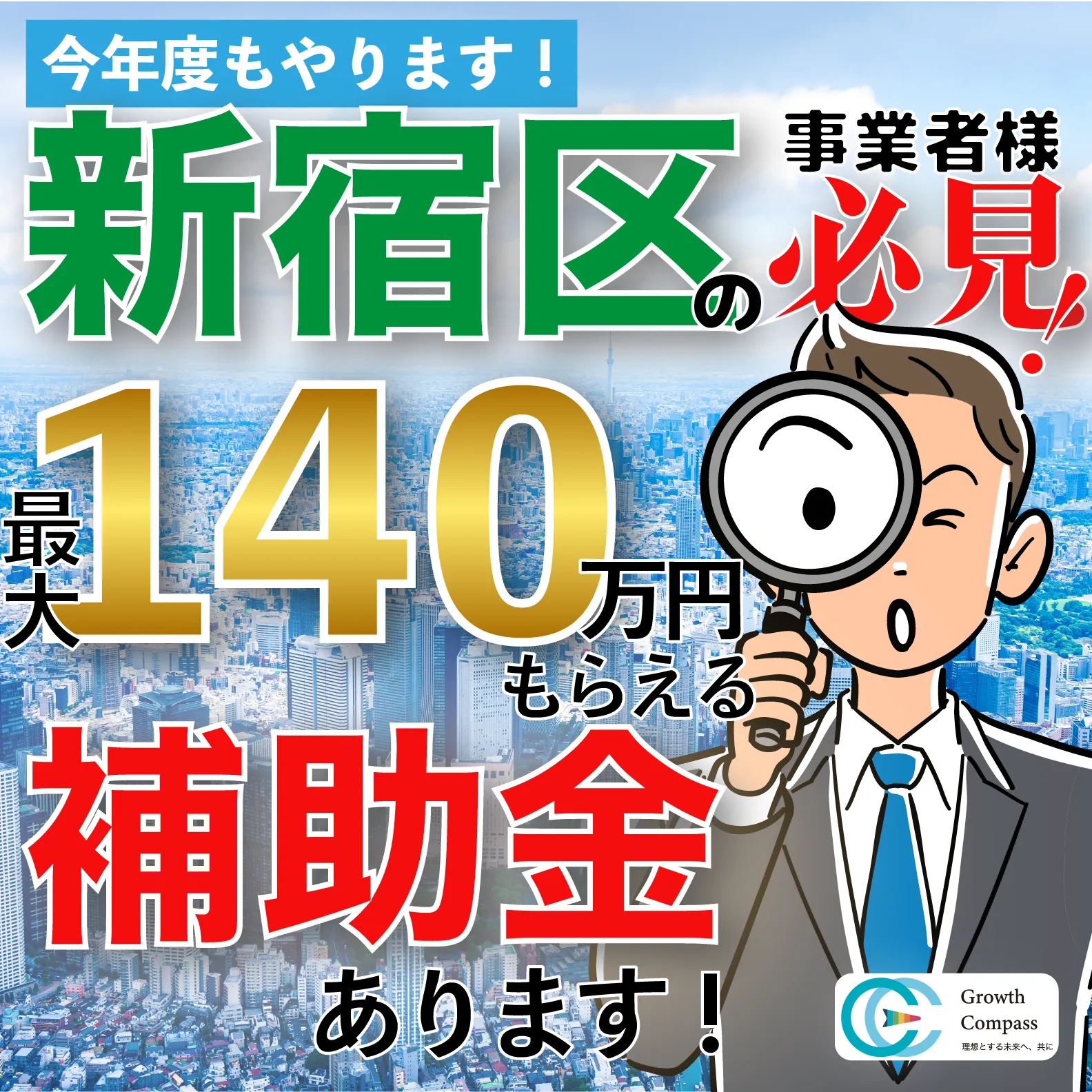
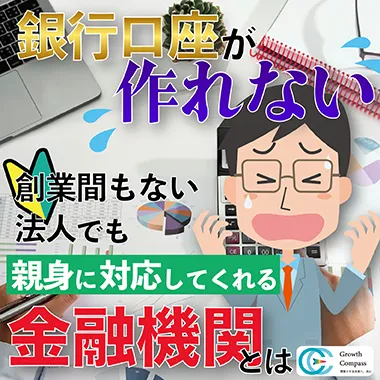




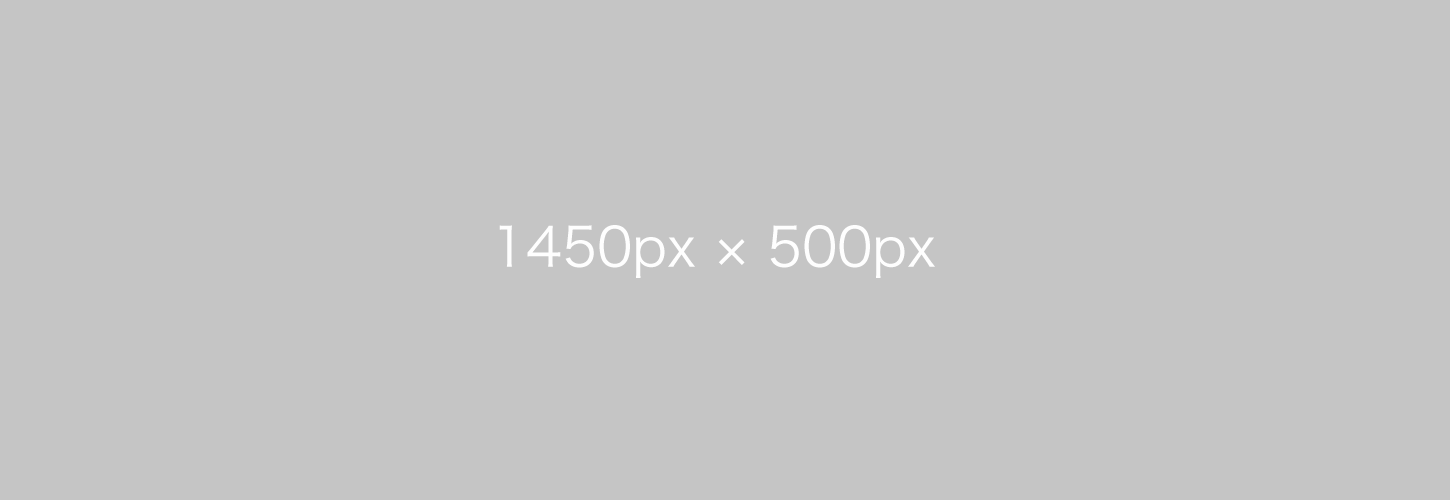
コメント